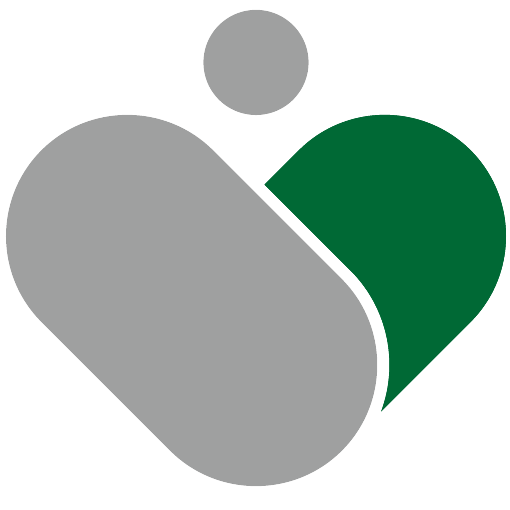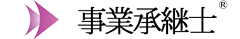医院開業サポートのご案内
医院開業の流れ
医院開業の大まかな流れをご紹介します。
- 1基本事項の決定
経営理念は、先生が「どういう目的でどのような内容で開業するのか?」をご自身の人生観や価値観をベースに決定します。
診療方針では、「どのような患者さんを対象に、どのような診療科目で開業するのか」を明確にしていきます。
開業に向けて様々な選択をしていく上で大変重要なものです。先生ご自身が考え文章化することをお勧めします。
- 2開業地の選定
開業物件を戸建てにするのか、それともテナントビルに入居するのかなどを検討します。
形態が決定したら、診療方針に沿って開業エリアを検討し物件を探します。当社でご紹介できる物件を多数ご用意しております。
同時にこの開業エリアで事業が成り立つ患者数が見込めるのか?診療圏調査を実施します。
診療圏の設定範囲により推計患者数が変わってきますので注意が必要です。
- 3事業計画書の策定
基本構想から開院までのスケジュール表を作成し全体を把握します。
開業に必要な資金を把握し、事業計画書を作成。何にどれだけの資金をかけ、その資金はどこから調達するのか?その結果、収支・資金繰りが可能なのかを検証します。調達先は、自己資金、借入金、リースなどです。
事業計画書は、開業後に事業の進み具合をみる上で大切な役割を果たします。
- 4銀行の選定と交渉
事業計画書は、金融機関から融資を受ける際の判断材料となります。
融資を受ける金融機関は、地方銀行、信用金庫、政府系金融機関、メガバンクなどが一般的です。
作成した事業計画書が、過剰投資になっていないか?収支計画は妥当か?生活費は考慮されているか?などが細かくチェックされます。
収入は控えめに、支出は多少多めにみて資金が回る堅実な計画を立てることが大切です。
- 5設計・施工について
ここで大切なことは、建築設計事務所が行う設計監理業務と施工業者が行う建築施工を、それぞれ別の業者に分離発注することです。
この分離発注は、先生が希望する医院建築が明朗な建築費で建てられる理想的な方式です。
当社では、医院建築やそれらに付随する関連費用の価格相場を把握しております。
院長に対し的確なアドバイスをさせていただきます。
- 6医療機器の選定使用する医療機器は、診療科目により当然異なります。自院に必要な医療機器を広汎に取扱うことができ、適正な価格提示で導入後のアフターフォロー、メンテナンスが確りできる業者を選択することが大切です。また、医療機器・備品などを導入する際、法定耐用年数や使用可能年数を見極め購入とリースを使い分けすることをお勧めします。電子カルテ・レセプトコンピュータ等はリース活用が一般的です。
- 7集患対策の準備
開業当初より多くの患者さんに来院していただくためには、事前の準備が必要です。
現在、勤務している病院の患者さんへは、いつどこで開業するのか早めに告知しておきましょう。
また、ホームページを早々に立ち上げ、医院のPRを兼ね職員募集をする医院も増えています。
一石二鳥かもしれません。
広告は、医療法を順守しながら、求人広告と開業広告の二度の広告を効果的に活用します。
- 8職員の募集と採用
医院の雰囲気は、そこで働くスタッフによって決まります。
職員募集は、書類選考や面接の結果、これぞと思う人材を採用します。
最近の傾向として、看護師は慢性的に不足している状況です。早めにアプローチをしておくことが大切です。
開業すると院長は事業主、職員は従業員という立場になります。院長は職員の生活を保証し働き甲斐のある職場を作る自覚が必要となってきます。
- 9開設の各種届出
医院開業には、開設許可申請届出が必要です。
その他にも保険医療機関指定、税務署、県市町村、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などへの届出も必要となります。
勿論、先生ご自身が全てを抱え込む必要はありません。当社が全面的にサポートいたします。
これらの届出が完了し医院開業がスタートすることになります。
医院開設時の各種届出書類一覧
医院開設時には、下記書類の届出が必要となります。
届出書類一覧表(個人開設・無床)
| 申請先 | 申請書類 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 保健所 | ⅰ.診療所開設届(個人開業の場合) | ⅰ.開設後10日以内 ⅱ.備付後10日以内 ⅲ.事前 ※検査日は開設届提出時に決定 |
| 厚生局 | ⅰ.保険医療機関指定申請書 | ⅰ.開設届出後、診療開始 予定月の前月締切日 ⅱ.算定開始月の締切日 |
| 福祉事務所 | ⅰ.生活保護法による医療機関の指定申請 ⅱ.特定疾患指定医療機関の指定申請 | ⅰ.保険医療機関指定後 ⅱ.保険医療機関指定後 |
| 社会保険事務所 | ⅰ.健康保険・厚生年金保険新規適用届 ⅱ.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | ⅰ.事業開始後5日以内 ⅱ.事業開始後5日以内 |
| 労働基準監督署 | ⅰ.労働保険関係成立届出 ⅱ.労働保険概算・確定保険料申告書 | ⅰ.事業開始後10日以内 ⅱ.事業開始後10日以内 |
| 公共職業安定所 | ⅰ.雇用保険適用事業所設置届 | ⅰ.事業所設置後10日以内 ⅱ.資格取得日の翌月10日まで |
| 税務署 | ⅰ.個人事業開廃等届出書 ⅱ.給与支払事務所等の開設届出書 ⅲ.所得税の青色申告承認申請書 ⅳ.青色事業専従者給与に関する届出書 ⅴ.所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 ⅵ.所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 ⅶ.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | ⅰ.事業開始日1ヶ月以内 |
| 労働基準監督署 | ⅰ.労災保険指定医療機関指定申請書 | ⅰ.保険医療機関指定後 |
| 市区町村 | ⅰ.事業開始等の届出書 | ⅰ.速やかに |
| 医師会 | ⅰ.入会申込書 | ⅰ.随時 |